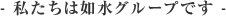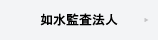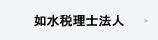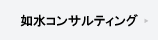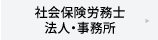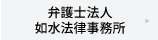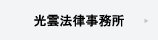2025.9.25.Thu
- コンプライアンス
カスタマーハラスメント②(謝罪編)
今回は、前回に引き続き、カスタマーハラスメントへの対応方法のうち謝罪について解説します。
1 謝罪を要求された場合の対応
⑴ 謝罪を要求された場合の一般的対応手順
①【聴取】 顧客の主張および要求内容のヒアリング
②【調査】 聴取を踏まえ、客観的事実関係等の確認
③【判定】 調査を踏まえ、要求内容の正当性について判定
④【回答】 判定を踏まえ、回答
⑵ 謝罪を行うべき場合
顧客から謝罪を求められた場合であって、
①【判定】において法的責任があると認められ、
②謝罪をすることが自社にプラスに働く場合 に初めて謝罪を行うべきです。
一方、顧客の感情に寄り添うための謝罪を行うことは状況に応じて検討すべきです。
そのため、道義的責任を認める謝罪、法的責任認める謝罪の2つを区別して、【判定】前に法的謝罪を行わないことが重要です。
⑶ 道義的謝罪
①道義的謝罪とは
道義的謝罪とは、一般的に顧客の主張する事実または要求を認める内容を含まず、顧客の感情に寄り添うために道義的な限度で行う謝罪で、法的責任について承認または発生させない謝罪のことを指します。
〇良い例
・ご不快な気持ちにさせて、申し訳ありません。
・ご不便をおかけしたことをお詫び申し上げます。
→顧客の主張する事実は認めておらず、感情に寄り添う限度でのみ謝罪をしています。
×悪い例
・申し訳ありません。すぐに返品交換させていただきます。
→顧客の要求に応じる法的責任を認めている。
・商品管理を怠り、申し訳ございません。
→顧客の主張する事実を認めてしまっている。
②道義的謝罪を行う場面
ア 企業に落ち度がない場合
イ 法的な過失・義務違反には至らない何らかの落ち度がある場合
※道義的謝罪のみをもって法的責任が肯定されることはありませんが、書面による謝罪を行う場合、文言により企業が法的責任を認めたと受け取られ、証拠とされるおそれもあるため、慎重な対応が必要です。
⑷ 法的謝罪
①法的謝罪とは
一般的に顧客の主張する事実または要求を認める内容を含み、法的責任を承認または発生させ得る謝罪のことを指します。
②法的謝罪を行う場面
ア 企業側に法的な過失・義務違反がある場合
かつ
イ 謝罪をすることが企業側にとって有利に働く場合 に法的謝罪を行うべきです。
③法的謝罪を行う場合の注意点
曖昧・包括的な内容によって事実や法的責任を認める範囲が不明瞭に拡大しないように注意が必要です。
法的謝罪は、訴訟において法的責任の認定において重く評価され、企業側に不利な証拠となる可能性が高いので、法的謝罪を行うかは慎重に検討してください。
2 念書等を要求された場合の対応
⑴ 顧客が書面による謝罪を要求してくる理由
企業側が非を認めたことを証拠として残すため、顧客が書面による謝罪を要求してくることがあります。
書面による謝罪をすると、裁判において証拠となるリスクやインターネット等で公開されるリスクがありますので、安易に応じないようにしましょう。
⑵ 書面による謝罪を要求された場合の対処法
顧客から書面による謝罪を要求された場合、企業側としては、原則として断るべきです。企業内で検討した結果、書面による謝罪をすることとなった場合には、
①法的責任と道義的責任の区別を意識した記載にする、
②謝罪する場合には何に対する謝罪であるかを明確にする、
ことにが重要です。
⑶ 具体的な文例
①法的責任を認める場合
「この度は当社製品の欠陥により、〇〇様がお怪我をしたこと、そのために〇〇様がお仕事を休まれたことについて、心よりお詫び申し上げます。」
②道義的責任を認めているにすぎない場合
「この度、〇〇様から当社製品の欠陥によりお怪我をされた旨のお申し出をいただきました。当社としましては、現在、当社製品に欠陥があったか否かを含め、慎重に調査を進めておりますので、ご返答まで今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。」
3 「誠意を見せろ」と言われた場合の対応
⑴ クレーマーが「誠意を見せろ」と要求することの意味
不当クレーマーは往々にして「金品や過剰なサービス、土下座」などを要求する言葉として「誠意を見せろ」という言葉を使用しています。
これは直接的に言葉に表してしまうと、強要罪(刑233条)や恐喝罪(刑249条)などが成立し得るため、「誠意」という曖昧な言葉を用いているのです。
クレーマーから「誠意を見せろ」と要求された場合には、以下のように対応しましょう。
①発信者が要求している「誠意」の中身を相手に確認します。
②「誠意」の中身の確認の可否にかかわらず、事実関係を確認した上で責任の判定をして回答(会社としての回答)をするまでは、対応者が独断で「誠意を示す」対応をしないようにします。
③ ②の「会社としての回答」が決まった場合には、企業側の対応としてその回答(対応)を行い、それ以外の要求は拒絶します。
※クレーム対応のプロセスに従って、企業の責任判定をし、その結果として、企業として行うべき対応を行えば、
企業としての誠意ある対応として十分です。回答の際には、「これが当社の誠意ある回答です。これ以上は応じかねます。」と過剰な要求を毅然と拒絶しましょう。
⑵ 要求の具体的内容が明らかにならない場合
「決められた時間」が過ぎていれば時間が過ぎたことを告げ、対応を打ち切ります。「これ以上は私の判断では回答できませんので会社において事実関係を確認した上で会社として回答をします」などと顧客に告げましょう。
4 初動対応を誤ってしまった場合の対応
⑴ 初動対応の誤りの例
・不適切な謝罪
・不必要な念書や合意書等の作成
・不当な要求の実現
⑵ 初動対応を誤り、不利な状況に陥った場合のリカバリー方法
①事実確認や法的責任を検討する前に責任を認めたと顧客から受け取られるような対応を行ってしまった場合
文書やメール等を送付し、法的責任はない旨、明確に伝えることが必要です。速やかに内容証明等を発送し、その合意書や念書等の効力を取り消しましょう。
②不当な要求に応じてしまった場合
本来は不当な要求に応じる法的義務は存在しないこと、今後は不当な要求に応じることはできないと毅然とした態度で伝えることが必要です。
⑶ リカバリーを行う者
初動対応を誤った者ではなく、別の従業員、または場合によっては弁護士による対応が有効です。
初動対応を誤った者が対応し続けると、顧客は以前発言したことと異なるではないかなどと、その理由を問うたり責め立てたりするなど、クレームを継続しやすくなります。
また、初動対応を誤った者も自身の発言や態度等で一度は顧客の不当な要求に応じてしまっているため、心理的に毅然とした対応(法的責任の不認容及び不当要求の拒絶)をとり続けることが難しくなってしまいます。
まとめ
カスハラ対策では、マニュアル化、従業員教育が重要です。
ex
・事実の確認をしっかりと行う
・ 記録を残す(証拠保全にもなる)
・ 安易な回答をしない
・ 対応する場合は複数人で
・ 毅然とした態度で対応する
福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。