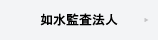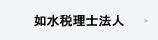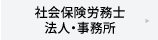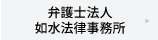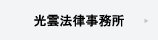Q 当社が所有している賃貸マンションで滞納が続いていたため、催促をしているのですが、電話も手紙もつながらず、部屋に行っても実際に住んでいるか分かりません。鍵は持っているのですが、勝手に開けて荷物などを出して新しい入居者に貸していいものでしょうか。
A まず、賃貸借の解除が認められるかどうかについては、「信頼関係の破壊」が認められるかによります。「信頼関係の破壊」が認められる場合には裁判をするということになりますが、今回のように賃借人と連絡がとれず、どこにいるか分からない場合には、前提として話し合いでの解決が困難と思われますので、訴訟を提起する必要性が高いといえます。
所在不明の者への裁判手続き
我々弁護士が調査を行う場合には、住民票が別の場所に移されていないか、という調査を行うこともありますが、住民票は元の住所のまま、ということもあります。
その場合、まず、賃貸借契約の解除の意思を伝えないといけないので、現住所宛に解除通知を送ります。通常は内容証明郵便で送りますが、相手が受領しない場合や不在で受領できない場合には返送されてしまいます。そのため、相手が受領しないことが予測される場合には、郵便受けに配送されたことを担保するために特定記録郵便を発送するという方法をとります。
所在不明者の探索方法ですが、一般的には、
・賃貸物件への訪問や郵便受け、水光熱メーターなど居住の有無の確認
・近隣住民や管理人への確認
・保証人などへの確認
などがあります。この調査の内容によって、居住が確認できる(こちらの連絡に応じないだけなのか)のか、居住の痕跡がないのか、によって訴訟を行う場合の手続きが変わってきます。
賃借人の居住が確認できる場合には、解除の通知も有効に到達したものと考えられますし、訴状の受領を拒絶したとしても、賃借人の居住が確認できる旨(生活の痕跡が認められる旨)の報告書を裁判所に提出した上で、書留郵便に付する付郵便送達という手段で訴状を送達することができます。
一方で、居住が確認できない場合には、賃借人の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に公示の方法による意思表示に関する申し立てを行い、相手の所在が不明と認められた場合には、解除通知書が裁判所に掲示されるとともに官報に掲載されるなどして解除の意思表示が到達したとみなす方法で解除を行うという方法があります。
ただし、どちらにせよ、その後訴訟提起を行うため、訴状の中で解除の意思表示を行うことで対応する方法が直截的です。
賃借人の居住が確認できない場合には、公示送達の方法により訴状を送達します。
これは、賃借人の居住が不明であることを調査結果とともに裁判所に報告書を提出し、裁判所の掲示板に訴訟提起の事実を掲示することで掲示から2週間の経過をもって訴状が送達したとするものです。
これによって訴訟が進行し、賃借人が裁判所に出頭しなかったとしても賃貸人の請求を認める判決が出され、この判決に基づいて強制執行などを行うこととなります。
このように、賃借人の所在が不明の場合には対応が煩雑ですが、裁判手続きを経ずに勝手に荷物を出すなどの自力救済は禁じられており、そのようなことを行うと民事や刑事の責任に問われる可能性もあるので、絶対に控えてください。
最近では、このようなリスクを避けるために、家賃債務保証会社などの活用も進んでいます。
福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。
Q 所有しているビルが老朽化し、建替えをしたいので次の賃貸借契約期間の満了をもって賃借人に退去してほしいと思っています。賃貸借契約期間の満了による場合であれば解除は認められるのでしょうか。それとも、賃借人の引っ越し費用など、いわゆる立退料の負担をすれば解除は認められるのでしょうか。
A 賃貸借契約は通常数年間程度の契約とされていることが多く、期間が満了すると契約が終了するようにも思われます。現に定期賃貸借契約の場合には、期間満了により当然に終了することとなっています。
一方で、普通賃貸借契約の場合には、賃貸借契約の終了には正当事由が必要とされています。この正当事由の判断には、
・建物の賃貸人及び賃借人が、それぞれ建物の使用を必要とする事情
・建物の賃貸借に関する従前の経過
・建物の利用状況及び建物の現況
・建物の明け渡しの条件(いわゆる立退料)
が考慮されます。
そのため、裁判になった場合には、建物の使用の必要性を前提に、これまでの経緯や立退料などの事情を総合考慮して明け渡しの是非が判断されます。オーナー側の視点に立つと、立退料を高額にしても、必ずしも明渡しが認められるわけではないということになります。
賃貸借契約終了の正当事由について
この正当事由については、強行規定といって契約書で修正できないとされていますので、いくら契約書に賃貸人の中途解約権などを定めていたとしても正当事由がない解除はできないため、期間満了による明渡しを確実に行いたいのであれば、定期賃貸借契約を締結することを心掛けなければなりません。
それでは、建物の老朽化が進んでいる場合に、建替えをするという事情は正当事由となるのでしょうか。建物の老朽化や耐震性能の不足、他のテナントとの競争力の低下という事情は賃貸人側から裁判でも主張されることが多く見られます。
実際に裁判においても、建物の建替えによる土地の有効利用は正当事由を基礎づける有力な事情と考えられており、賃貸人側の使用の必要性を基礎づける重要な事実となります。
実際に明渡しを進める場合には、オーナー側とテナント側で交渉が行われることが一般的であり、このような交渉経緯も正当事由の重要な要素とされていますので、オーナー側からすると誠実に交渉を行う必要がありますし、その中で移転を強いられるテナントの不利益を解消するための提案を行う必要があります。
普通賃貸借契約の終了の流れ(賃貸人請求の場合)
一般的に普通賃貸借契約を解消する場合には、期間満了の1年前から6か月前の間に賃貸人から賃借人に対して賃貸借契約を更新しない旨の通知を行い(借地借家法26条1項)、その前後で立ち退きに向けた条件面での交渉を行うこととなります。
交渉で解決がつかなかった場合には訴訟手続きの中で解決が図られることもありますが、この場合であっても裁判所は話し合いによる解決を調整するのが一般的です。
この話し合いの中で、退去を余儀なくされる賃借人に対して
・移転した場合の賃料の差額の補償(一定期間)
・移転先での工事等の費用
・移転に伴う案内等の費用
・引っ越し費用
などを行うことを前提に和解の協議がなされていきます。
最初の質問への回答としては、老朽化による建替えについては、建替えの必要性が認められる場合には解除が認められる場合もあるが、絶対に解除できるわけではないし、解除できる場合であっても、一般的にはオフィスの移転に伴う一定の費用が立退料として必要となることが多い、という回答となります。
福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。
賃貸借契約の解除の可否
Q 当社が所有している物件についてAに賃貸借をしていますが、最近賃料を滞納しています。前にも賃料を滞納したことがあり、契約書にも賃料を滞納した場合には解約できると記載しているため、賃貸借契約を解除しても問題ないでしょうか。
A 賃料の滞納があっても「信頼関係の破壊」が認められないと賃貸借契約の解除は認められません。
賃貸借期間中にテナントからの賃料が滞ることはよく起こりうるものです。最近では、居住用住居のみならず、商業用のテナントについても家賃債務保証会社と契約を行い、賃料が滞納されても家賃債務保証会社から支払いを受けるということも増えていますが、まだまだ居住用に比べると浸透度が低いのが現状です。
賃料滞納が数か月分積み重ならないようにこまめに賃借人と連絡を取りながら回収をしていくのが重要ですし、万一賃料の支払いを受けられなくなった場合に敷金でカバーできる範囲なのか確認しておくことも必要です。特に、テナントの場合は原状回復費用がかさむことが多いので賃料の滞納だけでなく、原状回復費用もカバーできるのかは重要な確認事項です。
では、テナントが賃料を滞納した場合に、賃貸借契約の解除は認められるのでしょうか。
賃料の支払いは賃貸借契約の重要な約束事ですし、賃貸借契約書でも賃料の支払いを怠ると解除できるとしていることが通常ですので、解除は認められそうにも思われます。
しかし、賃貸借契約は継続的な関係に基づくものであり、裁判例上、こうした契約については「信頼関係の破壊」がないと契約の解除はできないとされています。
一般的には、賃料を1~2か月程度滞納しただけでは信頼関係を破壊したとはいえないとされることが多く、3か月以上の滞納が目安とされています。
テナント(賃借人)が破産した場合の賃貸借契約の解除の可否
また、テナント(賃借人)が破産した場合は賃貸借契約の解除は認められるのかという相談もあります。
賃貸借契約の中には、賃借人が破産手続開始の申し立てをした場合や開始決定がなされた場合を解除事由としていることがよく見られますが、これは賃借人にとって不利なものとして裁判例上無効とされています。
一方で、破産にいたる会社は賃料を滞納していることもよくありますが、上で述べたように3か月程度の滞納があって、信頼関係が破壊されているとされれば、賃貸借契約の解除は可能です。
テナントが破産し、賃料の滞納状況から判断して賃貸借契約の解除が困難という場合には、賃貸人は破産した会社の判断を待つ必要がありますが、破産手続きが開始すると裁判所から破産管財人という者が弁護士の中から選任され、この破産管財人が賃貸借契約を解除するか、継続するかを決定することとなります。
破産管財人が賃貸借契約を継続すると決めた場合賃料がどうなるかということを疑問に感じられると思いますが、開始決定後の賃料については優先的に支払いを受けられる債権とされます。一方で、破産開始決定が出る前までの賃料については、このような優先的な支払いを受けられず、破産債権として届出を行うこととなりますが一般的にはかなり低い配当率での配当を受けるのみです。
ただし、敷金がある場合には、未払賃料を敷金から相殺することはできます。
福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。
今回は2024年6月に実施した業種別法務⑥不動産のセミナーで紹介した内容をもとにコラムを書いています。
Q1 最近の物価高に対応して、ビルのテナントとして入居している顧客に対して、賃料の増額を請求することはできるのでしょうか。
A 通常は顧客との間で賃料増額について協議を行い、話し合いで解決できない場合には、調停や訴訟などの法的手続きを行い、その手続きの中で解決を図っていきます。
賃料の増減額請求の要件
賃貸借契約の賃料は当事者の合意で決まるため、契約期間中は契約書記載の賃料に拘束されるのが原則です。
ただし、賃貸借契約は継続的な契約で長期にわたることも多いため、その間の景気動向や不動産市況などの経済事情により賃料が不相当な内容となることがあります。
そのため、借地借家法により、社会経済事情の変動で賃料が不相当になった場合には賃貸借の相手方当事者に賃料の増減(増額だけでなく、減額もある)を請求できる権利が認められています。
では、どのような場合に賃料の増減請求が認められるのでしょうか。
借地借家法は以下の3つを賃料が不相当となる事由としてあげています。
- 土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減
- 土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動
- 近傍同種の建物の賃料との比較
ただし、これらはあくまで例示列挙とされていて、その他の事情も合わせて賃料が不相当かどうかを総合的に判断します。
裁判例が他にあげている要素としては、
当事者が事業者か否か、その事業の規模
建物が居住用か営業用であるかなどの賃借建物の用途ないし性格
賃貸借契約締結の際における交渉の経緯並びに当事者の意思
契約締結後の状況
です。これらの要素を見ると、賃料の相当性の判断については、個別特別な事情や当事者の主観なども判断要素となっていることが分かります。
また、最後の賃料を決めたのがいつか、というのも重要な要素です。たとえば、2年前に賃料を増額・減額したというのも要素になりますし、2年前の更新の際に賃料を据え置いたということも判断要素とされます。
そのうえで相当賃料をどう定めるか、という点については、建物価格をベースに期待利回りや必要経費等を考慮して求める方式(利回り方式)や従前の賃料にその後の経済事情の変動率を乗じる方式(スライド方式)、近隣の賃貸事例と比較する方式(賃貸事例比較方式)などありますが、裁判実務ではこれらの方式を組み合わせながら総合的に判断しています。
賃料の増減額請求の手続き
では、実際に手続きが進められるとしたらどのように進むのでしょうか。
まず賃料増減請求は、最初は当事者間での協議が行われますが、任意の交渉で解決できない場合には、法的手続きをとられることがあります。
その場合には、調停前置主義といって、裁判ではなく、調停という裁判所での話し合いの手続きを経ないといけないとされています。この調停とは調停委員という2人の委員が間に入ってそれぞれの意見を聞きながら話し合いでの解決を探っていくという手続きです。
それでも解決できない場合には、訴訟提起をすることで、裁判所が相当な賃料の金額を判断することとなります。
仮に裁判になった場合、解決まで一定の時間がかかります。その間の賃料をどうするか、ですが、裁判が確定するまでは賃借人が自ら「相当と認める額」を支払えばいいとされています。
ですので、仮に賃貸人から賃料増額を請求を受けた場合であっても、賃借人は裁判で確定するまでは従前の賃料を支払えば足りますし、相手が受け取らない場合には、法務局に供託をするという対応も検討が必要となります。
福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。
今回はM&Aの中で、不動産について説明いたします。
法務DDの中で不動産に関する調査が重要性を持つかどうかは、対象会社が所有する不動産の位置づけによって変わってきます。
単に、資産として賃貸料収入を得るために持っている不動産については、財産的な価値評価は別として(財務DDなどで行うことはあるとしても)、法務DD的には本業に与える影響は小さいと判断されることも多くあります。
一方で、オフィスや工場などに使用している不動産については、
利用形態が所有なのか賃貸借なのか、
継続的な使用が本業の継続に必要なのか、それとも代替可能(移転の負担も含めて)なものなのか、
賃貸借契約とした場合に契約の継続が可能なのか、
賃貸借契約は不公平なものではないか(たとえば、創業者個人が所有する土地を高額で賃借していないか)
などという点が問題になってきます。
他方、土地については、土壌汚染などの環境に与える影響なども問題となりえますが、法務DDの検討範囲を超えるものでもありますので、実務的にはヒアリングでの確認や現地の外観を確認したり、という程度の対応が多く、より詳細な調査は専門業者に委ねるべきです。不動産の所在地や重要性によっては現地を見に行かないこともありますが、見に行ったところ、契約関係が不明な第三者の看板が土地上に設置してあったこともあり、現地確認が有効な場合もあります。
不動産の使用権原による検討事項
① (建物も)土地も所有の場合
建物も土地も対象会社が所有している場合や、土地を利用していて土地を所有している場合には、調査はそれほど複雑ではありません。
対象会社が所有していることを不動産登記で確認をするとともに、抵当権などが付されていないか謄本やヒアリングで確認を行います。
② 建物所有、土地賃貸借の場合
第三者の土地上に対象会社所有の建物が存在する場合には、土地利用の権利が確保されているのかについて確認が必要となります。
確認する事項としては
ⅰ土地の地上権ないし賃借権が確保されているか、
ⅱ土地の利用権に優先する抵当権などが設定されていないか、です。
ⅰの土地の利用権については、地上権よりも賃借権が設定されることが多く見られるため、賃借権の場合の注意点について説明します。
まず、土地の賃貸借契約が建物の所有目的である場合には、借地借家法が適用され、賃借人の権利が厚く保護されるため、借地借家法の適用がされる賃貸借契約かどうかという点は重要な検討項目です。一時使用目的や定期借地等に当たる場合には、借地借家法の一部が適用されないため、これらの事項に当たらないかについても検討が必要です。
賃貸借契約一般については、
・賃貸人が土地を賃貸借する権限を有しているのかという点の確認が必要です。一般的には土地の所有者に該当するか、不動産登記を確認することが多いですが、転貸借であるような場合には、不動産登記を確認しても転貸人が所有者でなく、賃貸借を行う権限が確認できないため、原賃貸借契約の締結についても確認となるほか、原賃貸借契約が解除されると転借人も退去しなければならないこととなるため、転貸借に伴う対象会社のリスクを適切に評価する必要があります。
・賃貸借期間や更新条項の有無、中途解約条項の内容なども確認を行い、事業の遂行途中に予期せぬ解約がなされるおそれがないかについての確認も必要となります。契約書上の問題も確認が必要ですが、具体的な解約のおそれがあるかヒアリングでも確認を行います。
・賃料や賃料の改定の条件、敷金の預託額や返還条件なども対象会社の財務面に影響を与える事項ですので確認を行います。
・その他、たとえば、会社の経営者が賃貸借契約の連帯保証人となっている場合には、売主からは連帯保証人の変更を求められる一方で、買主の代表者が代わって連帯保証人となるのか、賃貸人に対して連帯保証人の廃止を求めることができるのか、という点も検討事項となります。
③ (建物も)土地も賃貸借の場合
土地建物とも第三者所有の場合や土地のみを利用している場合に当該土地が第三者所有という場合には、②と同様に土地や建物の利用権が確保されているのかという点や賃借権等に優先する抵当権などが設定されていないかが確認事項となります。
ただし、②と異なるのは②の場合第三者所有の土地上に対象会社の建物があり、土地の利用権が認められなかったり、解消された場合に、建物の処分をどのようにするのかという検討事項が生じるのに対し、すべて第三者所有の場合にはそのような問題が生じません。
一方で、利用している土地や建物が代替性がない重要なものであれば、利用権が認められない場合や解消された場合のリスクは残りますので、そのようなリスクがどの程度具体的に生じているのか、という点について調査が必要となります。
福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。