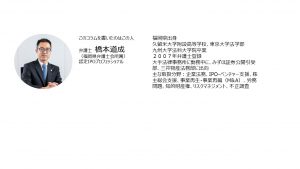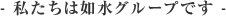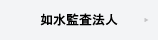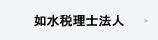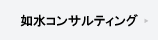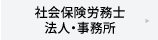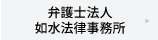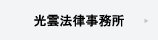2025.1.20.Mon
債権(売上)の回収について その2
債権(売上)回収が問題となったときに、するべきことについて3回に分けて解説しいます。
今回はその2回目です。
⑶任意の交渉
任意交渉の留意点は6つあります。
1つ目は、誰を交渉の場に出席させるかです。債権者側は、取引の実態を知っている担当者を同行させます。交渉の場で、債務者から反論が出た場合、その取引の実態に精通している者がいないければ、その場で確認できず、時間を要するためです。
一方で、債務者側には、担当者のみならず、支払いについての決定権・代表権のある者を同席させるよう求めます。そうしなければ、持ち帰って検討することになり、債務者側に時間稼ぎを許すことになってしまうからです。
2つ目は、情報収集です。任意交渉の時点では、双方とも歩み寄りの姿勢を持っているはずです。債権者としては、この機会に、任意の交渉が決裂したり、合意が履行されなかった場合に備えて、強制執行が可能な資産の情報を得るとよいです。債務者の取引銀行や主要取引先等について着目することが重要です。ただし、あまりに露骨に聞きすぎると、話し合いで解決する気はなく、情報収集に来たといった印象を与え、債務者に警戒されることになりますので、注意が必要です。
3つ目は、記録化です。交渉に臨む人数は、話す人・メモを取る人のように分業ができるよう、複数が望ましいです。また、複数人で交渉に臨むことで、言った・言わないの紛争を防止することもできます。相手方に無断で交渉内容を録音するといった方法も考えられ、このような録音であっても、必ずしも証拠能力が否定されるわけではありません。ただし、無断で録音を行ったことが判明すれば、信頼関係が崩れて交渉が決裂するリスクもありますので、録音の必要性は慎重に検討してください。
4つ目は、引き延ばしの防止です。債務者が破産や民事再生の申立てを行うために、債権者からの要望に対し、引き延ばしを図ることが考えられます。破産等の法的手続が始まってしまうと、債権回収が困難になるため、債権者としてはその前に少しでも回収を図る必要があります。
引き延ばしの防止の対策として、決定権のある者を交渉に同席させることが挙げられます。こうすることで、交渉の場で回答をするよう、債務者に要求できます。もし、やむを得ず後日回答するとなった場合でも、必ず回答期限を設けてください。
5つ目は、債務の確認です。任意交渉が決裂し、法的手続に入った段階で、債務者が何らかの抗弁を主張することがありますが、任意交渉の段階で、債務の内容を確認しておけば、そのような紛争を避けることができます。また、債務承認があったとして、時効の更新事由にもなります。時効の更新については、特別な合意書を作成しなくても、債権者作成の請求書の余白に、「上記請求内容に間違いはありません」と記載して、日付と署名・捺印をしてもらうなどの簡易な方法で問題ありません。その場合、捺印は代表者印が理想的ですが、紛争予防という観点からは、担当者の印鑑でもあるに越したことはありません。
6つ目は、違法行為を行わないことです。債務者が誠実に義務を履行しないとしても、自力救済や暴言、脅迫などは絶対に行わないでください。暴言や脅迫は勿論、自力救済も原則として違法です。
⑷相殺・担保からの回収
①担保
長期分割の弁済となる債権の支払確保のため、交渉によって新たに担保権を取得することが考えられます。当事者の契約により設定できる約定担保権は、抵当権・根抵当権(不動産)、動産譲渡担保・動産質(動産)、債権譲渡担保・債権質(債権)、連帯保証人(人的担保)等が挙げられます。
これらの約定担保権ですが、資金不足の会社の資産は、既に金融機関などが担保に取っていることがほとんどですので、担保に適した資産が残っていることがない場合もあります。
②相殺
相手が金銭を支払えなさそうな場合に、債権を回収する方法は3つあります。
1つ目は、相殺です。相殺する債権の弁債期が到来していれば、相殺は可能です。相殺の意思表示を行う場合は、内容証明郵便で相殺通知を送付するのが一般的ですが、相殺の意思表示には、条件または期限をすることができませんので、例えば、「〇〇までに支払わないときは相殺する」といった記載はしないようにしてください。
2つ目は、代物弁済(債務の弁済に変えて債務者の資産を譲り受けること)です。代物弁済は特に指定しない限り、給付した物の価格にかかわらず、債権全部が消滅してしまいます。これを避けるには、「売買代金債権100万円のうち50万円の支払いに変えて〇〇を引き渡す」というように、代物弁済により消滅すべき債権の範囲を特定しておく必要があります。逆に、物の価格が債権に比べて過大であるときは、その過大な部分について不当利得返還請求がなされる可能性もあります。そのため、消滅する債権と代物弁済を受けるものの価格とは適切なバランスをとっておきましょう。
3つ目は、債権譲渡です。債務者が第三者に対して有する債権を債権者が譲り受けるときは、債権譲渡の対抗要件を具備する必要があります。債権譲渡の対抗要件は、譲渡人からの通知または債務者の承諾です。
ただし、上記手段は後日、詐害行為(債務者が債権者を害することを知りながら、自己の財産を減少させる行為)として争われるおそれもある点には注意が必要です。
福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。