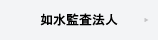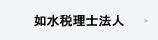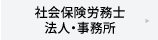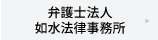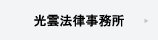今回は製造業で注意すべきポイントについて、Q&A形式で説明したいと思います。
1―1 秘密保持契約
Q:秘密保持契約の原案をチェックするとき、どのような点に注意して検討すべきでしょうか?
A:相手方との取引実態や開示予定の秘密の重要性などを踏まえ、契約の目的、秘密情報の定義、開示先の例外、契約の有効期間などの条項について、慎重に検討することが必要です。ネットではたくさんの秘密保持契約書のひな型を見ることができますが、内容を確認せずに確認するのは避けましょう。
Q:秘密保持契約の目的で注意すべきポイントは何ですか?
A:目的の範囲が広すぎると秘密保持義務を課した意味が弱まる一方で、狭すぎると目的外利用になるケースが増えてしまうので、バランスが求められます。
Q:秘密情報の範囲は、どのように定めたらよいでしょうか?
A:自社が主な開示主体であれば、広く設定したほうが一般的には有利です。一方で、相手方が主な開示主体であれば、秘密の範囲を明確かつ限定するために「秘密」の記載などで特定を要するとしておくべきです。
Q:秘密保持契約の有効期間の定めで気をつけるべき点はありますか?
A:開示済みの秘密情報を保護するために始期と終期には注意してください。
契約を締結する前に秘密情報の受け渡しがある場合は、始期を契約締結時としてしまうと、契約締結前に受け渡しがなされた秘密情報が契約で保護されなくなってしまいます。
※過去のコラムでも、秘密保持契約書を取り扱っておりますので、そちらも併せてご参照ください。
1-2 1回限りの契約
Q:1回限りの契約でも、契約書を作成しないといけませんか?
A:契約は、一般的には申込みと承諾の意思表示の合致で成立するため、契約書の作成は必須ではありません。注文書と請書でも契約は成立します。
しかし、注文書に記載されている契約条項の内容を確認せずに請書を送付すると、その内容で契約が成立してしまうので注意が必要です。
注文書に規定しない事項については、民法または商法などの任意規定が適用されることになるので、自社にとってそれらの規定よりも有利な規程を盛り込むことができるかという観点で検討します。
下請法の適用がある場合には、書面の交付や支払期日の定めなど、別途義務が生じるので下請法の適用対象であるかには注意をしてください。
1-3 取引基本契約書
Q:基本契約書を取り交わす意義は何ですか?
A:同一の当事者間で反復継続して同種の取引を行う際には、特別の事情がない限り、あらかじめ定められた同じ内容で取引をすることが簡便です。
また、基本契約書を取り交わすことで、当事者が不特定多数の相手と取引を行う際に、一括して共通の対応をすることも可能となります。
個別の取引ごとに異なる条項については、取引時に注文書・請書または個別契約で定め、共通事項は基本契約書をあらかじめ取り交わしておくことで、個別の取引のたびに契約書を取り交わす手間を省くことができます。
Q:自社ひな型を作成する場合の留意点は何ですか?
A:法令などに基づく制限が課される場合がある点が挙げられます。
例えば、下請事業者との契約では、下請法の規制にも留意する必要があります。
あまりに自社に有利な条項にすると、相手方から多くの修正を求められ、契約交渉が長引いてしまうおそれもありますので、有利にすればするほど良いというわけではありません。
Q:相手方ひな型を用いる場合の留意点は何ですか?
A:自社に不利な条項が含まれていても、全ての条項を修正するのは困難なので、修正を求める条項に優先順位を付けて交渉に臨みましょう。
自社が対応できない点、受け入れるとリスクが大きい点など、修正が必須な条項のために、重要度の低い条項は譲歩するなどのバランスが求められます。例えば、管轄裁判所が自社から遠い場合であっても、日本国内である限り対応できないということは考えにくいため、優先順位は低くなるといえます。
Q:力関係の差が大きく、相手方のひな型を受け入れざるを得ない状況である場合には、どのような手段が考えられますか?
A:保険をかけてリスクに備えておいたり、仕入れた商品を顧客に売却している事業者であれば、顧客との間の基本契約書と同様の内容の基本契約書を仕入先との間で結ぶなどの方法が考えられます。
1-4 印紙税
Q:印紙税とは何ですか?
A:印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成する契約書や領収書などに課される税金で、印紙税法別表第一課税物権表に記載されている20種類の文書が課税対象です。
印紙税の負担者は、印紙税が課される文書を作成した人であり、原則として、「課税文書に記載された作成名義人」です。
印紙税法は、日本の国内法なので、その適用範囲は日本国内に限られ、課税文書の作成場所が国外であれば、印紙税は課されません。
Q:請負契約と委任契約はどのように区別しますか?
A:前提として、請負契約書は課税文書であり、委任契約書は不課税文書です。
契約書のタイトルではなく、実質的な内容からいずれにあたるかを区別しますが、委任契約であっても、受任者の報告義務の一環として、報告書の交付が必要とされる場合があるため、成果物の有無で区別をすることは困難です。
そこで、「仕事を完成することを約し」たかどうかについて、個別具体的に判断することになります。
2-1 知的財産権
Q:特許権の成立要件や効力について教えてください。
A:特許出願をし、特許庁における審査を経て特許査定され、特許料の納付をすることで、特許権の設定登録ができます。
特許権の登録がされると、特許庁により発行される特許公報により特許の内容が公開され、特許公報はインターネットなどで誰でも閲覧が可能です。
特許権者は発明品の製造・販売を独占することができ、第三者が特許権を侵害する行為をした場合には差止めや損害賠償請求をすることができます。
特許の内容が公開されることで、競合他社が製品開発時に特許の内容を回避させるなどといった事実上の抑制力もあります。
2-2 オープン&クローズ戦略
Q:オープン&クローズ戦略とは何ですか?
A:自社の技術について、技術内容が公開される特許として保護するのか(オープン戦略)、それとも秘密として管理してノウハウとして保護するのか(クローズ戦略)を決定するものです。
オープン戦略をとった場合、特許権の登録後は、特許公開制度により特許権の内容が公開され、模倣のリスクが発生します。また、特許権の効力は出願から20年なので、権利の有効期間満了後には第三者も合法的に特許権の内容を実施されるというリスクがあります。
一方でクローズ戦略をとり自社技術を営業秘密とする場合、市場が小さければ大きな利益は期待できないうえ、情報漏洩などに対する対策が必要となります。
これらを踏まえて、事業戦略に鑑みて、特許権登録をして独占・排他的効力を発生させるか、営業秘密として半永久的に秘匿するかを判断することが必要です。
Q:オープン戦略とクローズ戦略のいずれを採用すればいいか、判断軸はありますか?
A:他社の新規参入が見込まれない自社のコア技術については特許出願をせず営業秘密としてブラックボックス化し(クローズ戦略)、
他社の新規参入のリスクがある分野については他社に先んじて特許出願を行って競争優位性を確保し(オープン戦略)、
自社の製造キャパシティ以上に市場の拡大が見込まれる分野については特許権の積極的なライセンス・アウトによる市場の拡大とライセンス収益を実現することが望ましいです。
2-3 営業秘密
Q:不正競争防止法で保護される「営業秘密」の効果とその要件は何ですか?
A:「営業秘密」として保護されると、不正競争者に対する差止請求、損害賠償請求等ができます。
不正競争防止法における「営業秘密」とは、①有用性、②非公知性、③秘密管理性を全て満たすものです。
①有用性とは、その情報が客観的にみて、事業活動にとって価値があることです。
一般的には、非公知性・秘密管理性を満たす企業内の情報は、有用性も認められます。ただし、公序良俗に反する内容の情報は有用性が否定されます。
②非公知性とは、「当該営業秘密が一般的に知られた状態となっていない状態、又は容易に知ることができない状態」とされています。
リバース・エンジニアリング(既存の製品の分解や分析などを行い、その動作原理や製造方法、設計、仕様の詳細、構成要素などを明らかにすること)によって非公知性が欠如するかについては、「一般的な技術手段を用いれば容易に製品自体から得られるような情報」であれば非公知性を失うとされる一方、「専門家により、多額の費用をかけ、長期間にわたって分析することが必要であるもの」については非公知性が失われないとされています。
③秘密管理性は、3つの要件の中で最も重要とされています。
秘密管理性の判断において、判例の傾向としては、
㋐アクセス権者の限定・無権限者によるアクセスの防止(例:鍵のかかる棚に保管しておく、パスワードをかけておく)
㋑秘密であることの表示・秘密保持義務の設定
㋒組織的管理(㋐、㋑の措置が機能するように組織としての管理を行っていること)
の3つの管理を全て実行することが必要とされています。
2-4 職務発明
Q:職務発明制度について気を付けるべきポイントは何ですか?
A:前提として、会社は、従業員が行った発明を当然に特許出願できるわけではないため、特許を受ける権利を発明者から取得するなどしなければなりません。
あらかじめ従業員との契約ないし就業規則などに職務発明に係る特許を受ける権利の帰属について定めておけば、使用者は、職務発明に係る特許を受ける権利を、職務発明が完成した時点で原始的に会社に帰属させることができます。
発明報酬は、金銭に限らない相当の利益を与えることも可能です。しかし、確認の意味で譲渡証書などの書類を従業員から取得している会社や、金銭以外の報奨を追加していない会社も相当数残っているのが実情です。
福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。
成果物に関する権利の帰属
⑴ 成果物に関する権利の帰属
委託業務の遂行過程で知的財産権が生じうる場合、何も定めがなければ権利の帰属をめぐって争いが生じるリスクがあります。そのため、権利の帰属先を明確に定める必要があります。
特許法や著作権法では、特許権や著作権などの知的財産権は、原則として発明者や著作物を創作した者に帰属します(特許法29条1項、著作権法17条、2条1項2号)。そのため、委託業務の遂行過程で知的財産権が生じた場合、特に定めがなければ、これらは業務を遂行した受託者に帰属することとなります。
委託者に有利にする場合には、委託した業務の遂行過程で生じた権利を自由に行使できるよう、「本委託業務の遂行過程で生じる知的財産権は、全て委託者に帰属する」と定めるとよいでしょう。
一方、受託者としては自らが遂行した業務の過程で生じた知的財産権を自由に行使できるよう、「本委託業務の遂行過程で生じる知的財産権は、全て受託者に帰属する」と定めるとよいでしょう。この場合、委託者には業務委託の目的の範囲内で使用権を許諾するという条項を入れること委託者の権利を確保します。
著作権法上、注意しないといけないこととして、翻案権(著作権法27条)と二次的著作物の利用に関する権利(同法28条)については、「権利を移転することを示さなければ、譲渡した者に留まると推定する」とされている点があげられます(同法61条2項)。
そのため、権利の帰属先を定める際に、「著作権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む)」と明記する必要があることに注意してください。
⑵ 第三者の知的財産権の侵害について
委託者としては、成果物が、他人の知的財産権などの権利を侵害している場合、権利者からクレームや侵害訴訟等を提起されるリスクがあります。これを防ぐため、「成果物が他人の権利を侵害しないこと」を受託者が保証することを定めるとよいでしょう。これにより、万一、成果物が第三者の権利を侵害するものであったときは、受託者に契約違反を理由に、損害賠償や解除を求めることができます。
また、委託者が権利者から訴訟を提起された場合は、訴訟に応じなければならないなど、不利益を被るおそれがあります。
そのため、委託者としては、「第三者の権利に関する紛争が生じたときは、受託者がその責任と費用負担において当該紛争を処理し」、「委託者が紛争の当事者となった場合には、受託者は、委託者に対し、委託者が被った一切の損害を賠償しなければならない」と定めるとよいでしょう。
一方、受託者としては、成果物に、他人の知的財産権が含まれているかどうかを確認することができないなど、第三者の知的財産権を侵害する可能性を排除することが難しい場合は、「成果物が、第三者の権利を侵害しない」という条項を削除する必要があります。その上で更に、「成果物が、第三者の権利を侵害しないことを保証しない」と定めるとよいでしょう。ただし、これも経験上、相手方から「保証する」と修正を要望されやすい条項です。
業務遂行状況の報告義務
(1)民法の原則
民法では、準委任契約型の業務委託契約の場合、受託者は、委託者の請求に応じて、業務の遂行状況を報告しなければなりません(民法645条)。
一方で、請負契約型の場合は成果物を完成させるための手段は受託者に委ねられているため、受託者はこのような報告義務を負いません。
(2)報告義務に関する条項例
委託者としては、いずれの場合にせよ、委託した業務がどのような状況にあるのか、必要に応じて把握できるように、「受託者は、委託者の求めに応じて、本委託業務の遂行状況を委託者に報告しなければならない」と定めると有利です。
他方で、受託者としては、報告に応じることが難しい場合もあるため、このような報告義務を負わない旨を定めるか、そのような修正が難しい場合は、「必要な範囲で報告しなければならない」と定めるなど、報告する範囲を限定すると有利です。
また、委託者としては、期限までに業務を行ってもらう必要がある場合には、受託者が予定通りに業務を遂行することができないときは、早い段階で何らかの対応策を講じなければなりません。
そこで、「受託者は、本契約期間中に本委託業務を遂行することができないことが判明した場合、直ちに委託者に報告し、委託者の指示を受けなければならない」と定めるとよいでしょう。
(3)立ち入り検査に関する条項例
さらに、委託者として、受託者の業務の遂行状況をより適切に把握するため、「委託者は、本委託業務の遂行状況について監査をすることができ、必要に応じて、受託者の事業所において、立入検査をすることができる」と定めることもあります。
他方で、受託者としては委託者に監査権や立入検査を許容すると、営業秘密や顧客情報などが流出するリスクがあるため、このような定めは削除するか、削除が難しい場合には、「受託者の同意」や「受託者の事業に支障を与えないこと」を条件とするのが望ましいです。
再委託
(1)民法の原則
準委任契約においては、民法では、受託者は、「委託者の承諾」又は「やむを得ない事由」があるときでなければ、再委託することはできません(民法656条、644条の2 第1項)。一方で、請負契約においては、民法上、特に再委託は禁止されていません。
(2)再委託の承諾に関する条項例
いずれの場合にせよ、委託者としては、自らの知らないところで、受託者以外の他人に業務を遂行されたくない場合には、「受託者は、委託者の事前の承諾なく、再委託してはならない」と定める必要があります。このとき、同意の有無をめぐる争いを防ぐため、委託者の同意方式を「書面」とする旨を確認的に定めるとよいでしょう。
他方で、受託者としては、必要に応じて自由に再委託できるように、「受託者は、本委託業務の遂行に必要な範囲で、再委託できる」と定めると有利です。
(3)再委託先の責任に関する条項例
委託者としては、再委託を許容した場合には、再委託先が契約の定めに違反し、不利益をうける恐れがあります。これを防ぐために、「受託者は、再委託先に対して本契約上の受託者の義務と同等の義務を負わせる」と定めると有利です。
また、再委託先によって損害を被った場合に、受託者に民法上の債務不履行がなければ、損害賠償を請求できないおそれがあります。そこで、「再委託先によって委託者に損害が生じたときは、受託者も責任を負う」と定めることが望ましいです。
福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。
今回はNDA(秘密保持契約書)に続いて、2回目の契約書の読み方に関する説明のその1です。
今回取り上げる業務委託契約書も、契約書チェックをする際によく見る契約です。
業務委託契約の法的性質
まず、法的な位置づけとして、業務委託契約は、準委任又は請負もしくはその中間的な契約として位置づけられています。
民法では、準委任契約では、委託者が「事務を処理すること」を受託者に委託し、受託者がこれを承諾することによって効力が生じます(民法643条、656条)。
一方、請負契約では、受託者が「成果物を完成させること」を約し、委託者がその結果に対して報酬を支払うことを約することによって効力が生じます(民法632条)。
事務処理というプロセスに重点を置くか、成果物の完成という結果に重点を置くかによって準委任に近い契約なのか、請負に近い契約なのかという点が変わってきます。
まず、いずれの場合でもどのような業務を委託するのかを定めておく必要があります。
特に、業務内容をめぐる当事者間の認識の相違によってトラブルが生じることを防ぐため、どういった業務を委託するのか、具体的に定める必要があります。
このとき、委託者としては、依頼した業務を遂行するために必要となる雑多な仕事に関しても受託者に対処してもらえるよう、「その他委託業務に附帯関連する一切の業務」も業務内容として確認的に定めておくといいでしょう。
成果物の完成義務
上で説明したとおり、プロセスと結果のどちらに重点を置くかによって準委任に近いか、請負に近いかが変わってきます。
そして、結果に重点を置く場合には、委託者としては、成果物が契約の内容に適合しなかった場合に受託者に対して責任を追及できるよう、「受託者は成果物を完成させる義務を負う」と定めるとよいでしょう。
一方、受託者としては、成果物を完成させることができるかどうかが分からない場合は、「受託者は、成果物の完成義務を負わない」と定めるとよいですが、このような条項があると完成義務を負う内容への修正の要望が生じることも多いです。
法令等の遵守義務
また、委託者としては、委託者が遵守すべき法定等の規則を受託者にも遵守させた上で業務を遂行させることができるよう、「受託者は、本委託業務の遂行に関して委託者に適用される法令等の規則を遵守しなければならない。」と定めることがあります。
一方、受託者としても、法令遵守はある意味当然の義務とはいえますが、業務を遂行するにあたって、どのような規則を守る必要があるのかを明確にするために、
「委託者は、本委託業務の遂行に関して委託者に適用される法令等の規則の内容を通知しなければならない」と定めることもあります。
⑴ 民法の原則
委託料をめぐってトラブルにならないように、金額を明確に定める必要があります。
また、契約が途中で終了したときのトラブルを防ぐため、「委託料が履行割合に応じて発生するのかどうか」を定めておくとよいでしょう。
民法では、準委任契約でも請負契約でも、委託者の責任によらずに、契約が途中で終了したときは、委託者は履行割合、もしくは仕事の結果のうち可分な部分の給付によって受けた利益の割合に応じて、報酬を支払わなければなりません(民法656条、648条3項、648条の2第2項、634条)。
なお、これは、受託者の責任で契約が途中で終了したときも同様です。
一方、委託者の責任で契約が途中で終了したときは、委託者は報酬の全額を支払わなければなりません(同法536条2項)。
⑵ 委託者の帰責性によって契約が途中で終了したときの修正
上で述べたように、民法では、委託者の帰責性によって、契約が途中で終了したときは、委託者は報酬の全額を支払わなければなりません。
そのため、委託者に有利にする場合には、委託者の責任で契約が終了した場合でも、履行割合に応じて報酬を支払えば済むように、「委託者の帰責事由によって本契約が終了した場合、委託者は、履行割合を乗じた金額を受託者に支払う」と定めるとよいでしょう。
一方、受託者に有利にする場合には、自らに責任がない限りは報酬の全額を請求できるように、「受託者の帰責性によらずに契約が途中で終了したときは、委託料の全額を請求できる」と定めるとよいでしょう。
民法の規定通りとする場合は、「委託者の帰責事由によって、本契約が終了した場合、委託者は委託料の全額を支払う」と定めておきます。
⑶ 受託者の帰責性によって契約が途中で終了したときの修正
民法では、受託者の責任によって、契約が途中で終了したときであっても、委託者は履行割合、もしくは仕事の結果のうち可分な部分の給付によって受けた利益の割合に応じて、報酬を支払わなければなりません。
委託者としては、受託者の帰責性によって契約が途中で終了した時は、報酬を支払わなくても良いように、「受託者の帰責性によって契約が途中で終了したときは、委託料は発生しない」と定めるとよいでしょう。
福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。