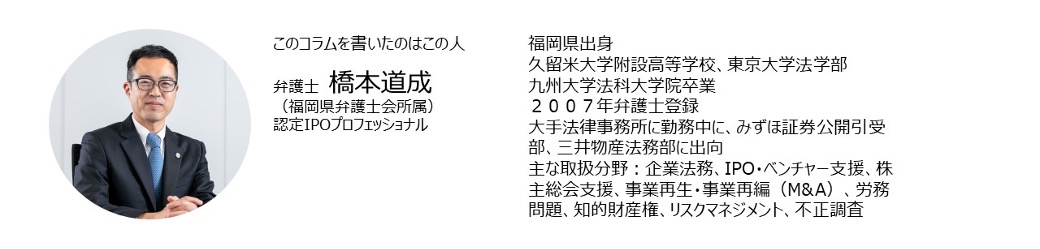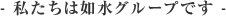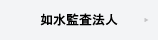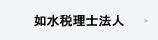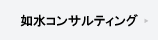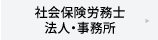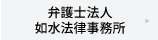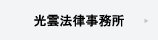令和8年1月1日から施行される「中小受託法」(改正下請法)の主な改正点と、それに伴う実務対応のステップについて説明いたします。
主な改正ポイントとして、以下の6点について説明します。
- 「下請」等の用語の見直し
- 下請法の適用基準の追加(従業員数基準の導入)
- 一方的代金決定の禁止規定の追加(価格協議の義務化)
- 下請代金等の支払条件の見直し(手形払いの原則禁止)
- 物流分野における下請法の適用対象取引の拡大
- その他(細かな変更点)
①「下請」等の用語の見直し
まず法律の名称自体が変わる点が大きな特徴です。これまで「下請法」と略されてきた「下請代金支払遅延等防止法」は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」という名称に改められます。通称としては「中小受託法」と呼ばれます。
名称変更の背景には、「下請」という用語が発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えるという指摘があり、用語の見直しも行われることになりました。
具体的には、これまで使用されてきた用語も以下のように変更されます。
- 「親事業者」は 「委託事業者」 に
- 「下請事業者」は 「中小受託事業者」 に
- 「下請代金」は 「製造委託等代金」 に
企業としては、契約書や社内規定などで使用している用語を、この新しい用語に合わせて見直すことが推奨されます。
② 適用基準の追加
適用基準の追加は、「下請法逃れ」と呼ばれる、法の適用を意図的に免れる行為に対応するために行われました。
これまでの下請法では、適用対象となる取引の範囲は、事業者の資本金の額と取引内容の2つの要件で定められていました。しかし、会社法における資本金制度の柔軟化や減資手続きの緩和が進んだ結果、事業規模が大きな事業者であっても、少額の資本金で会社が設立されたり、減資によって法の適用対象から外れたりする事例が指摘されていました。
この問題を解決するため、中小受託法では、従来の資本金基準に加えて、常時使用する従業員数を新たな適用基準として追加しました。
具体的な基準は以下の通りです。
- 物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合:
◦委託事業者(旧親事業者)が「常時使用する従業員数が300人超」 で
◦中小受託事業者(旧下請事業者)が「常時使用する従業員数が300人以下」 の場合
- 上記以外の情報成果物作成・役務提供委託を行う場合:
◦委託事業者(旧親事業者)が「常時使用する従業員数が100人超」 で
◦中小受託事業者(旧下請事業者)が「常時使用する従業員数が100人以下」 の場合
この従業員数基準の追加により、これまで下請法の適用対象外だった事業者との取引が、新たに適用対象となるケースが大幅に増加すると予測されています。企業としては、自社の取引先について、新たに中小受託事業者に該当する企業がないか、従業員数を確認し、対象取引を洗い出す作業が急務となります。
③ 一方的代金決定の禁止、価格協議の義務化
一方的代金決定の禁止は、近年の物価高騰やコスト上昇、特に労務費、原材料価格、エネルギーコストなどの上昇局面で、価格転嫁が適切に行われない問題に対応するために新設されました。
現行の下請法にも「買いたたき」を禁止する規定はありますが、これは「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」を禁止するものでした。しかし、単価等の見直しをせずに下請代金を据え置く行為は、それだけでは直ちに代金が引き下げられる場合にあたらないこともあり、買いたたきの要件に該当しない場合もありました。これが下請事業者の経営を圧迫しているという指摘がありました。
そこで、中小受託法では、委託事業者(旧親事業者)と中小受託事業者(旧下請事業者)との間で実行的な価格交渉がなされることを確保するという観点から、新たな禁止規定を追加しました。
具体的には、中小受託事業者の給付に係る費用の変動が生じた場合などに、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が以下の行為を行うことを禁止します。
- 協議に応じないこと
- 協議において中小受託事業者が求めた事項について必要な説明や情報を提供しないこと
- 一方的に製造委託等代金の額を決定すること
これらの行為によって中小受託事業者の利益を不当に害することが禁止されます。つまり、これまでは価格が「著しく低い」場合に問題とされていましたが、今後は価格決定プロセスにおける不当な行為も規制されることになります。
委託事業者には、価格協議の要請があった際には適切に応じ、必要な説明や情報を提供し、一方的な決定を避ける義務が生じます。これを怠ると、公正取引委員会から是正勧告を受け、企業名などが公表される可能性があります。
④ 支払条件の見直し
支払条件の見直しは、中小受託事業者の資金繰りを改善し、より確実な代金受領を目的としています。
これまで下請法の下では、手形やファクタリング、電子記録債権などを用いた支払いが認められていました。
しかし、政府は令和3年の閣議決定で約束手形の利用廃止を目標に掲げています。加えて、電子記録債権や一括決済方式による支払いでは、下請代金の全額を現金で受領するまでに、給付受領日から起算して60日を超える期間を要することが多いという問題点が指摘されていました。現行法では、支払期日は受領日から60日以内と規定されていますが、手形決済の場合、手形交付から現金化までにさらに時間がかかることが課題でした。
中小受託法では、これらの問題に対応するため、以下の変更が行われます。
- 支払手段として手形払いは認めないこととされました。
- 金銭以外の支払手段(電子記録債権、ファクタリング等)についても、支払期日までに製造委託等代金(旧下請
代金)の満額の現金と引き換えることが困難であるものは認めないこととされました。
これにより、委託事業者は、手形払いを廃止し、現金またはそれに準ずる、支払期日までに確実に現金化できる支払方法に切り替える準備が急務となります。
⑤ 物流分野への適用拡大
物流分野への適用拡大は、運送業務における取引の適正化を図ることを目的としています。
平成15年の下請法改正で、役務提供委託が対象取引に追加され、元請運送事業者と下請運送事業者の間の取引は下請法の対象となりました。しかし、発荷主(荷物の所有者や発注者)から運送事業者への運送業務の委託は、これまで下請法の適用対象外とされていました。これらの取引は独占禁止法に基づく「物流特殊指定」によって規制されてはいましたが、買いたたきや、契約にない荷役の無償強制、長時間の荷待ちといった問題が依然として高止まりしており、運送事業者が不利益を被るケースが多数指摘されていました。
これらの課題に対応するため、中小受託法では、「特定運送委託」を新たに下請法の適用対象取引とすることとされました。
「特定運送委託」とは、事業者が、業として行う販売、製造若しくは修理の目的物たる物品、または情報成果物が記載等された物品の販売等をした場合に、取引の相手方に対する運送の行為の全部または一部を他の事業者に委託する行為を指します。
⑥ その他改正点
上記の主要な改正点の他にも、いくつか重要な変更があります。
- 「製造委託」の対象物の追加: これまで対象物に含まれていなかった木型、治具等も、「製造委託」の対象物に 追加されることになりました。
- 減額された代金分の支払についても遅延利息の対象となること: 製造委託等代金が減額された場合、その減額された代金分の支払いについても、中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をする日 までの期間について、遅延利息の対象とされます。
- 電磁的方法による書面交付の容認: 現行の下請法第3条に基づき交付が義務付けられている書面について、中小受託事業者(旧下請事業者)の承諾なくして電磁的方法により提供できるように変更されます。
- 是正済み違反に対する再発防止勧告: 委託事業者(旧親事業者)が中小受託法第5条に規定する禁止規定に違反した場合、たとえその違反行為が既に是正されていたとしても、公正取引委員会が再発防止策を勧告できるように規定が新設されました。
まとめ
これらの改正を踏まえて、企業、特に「委託事業者」が実務で気を付けるべきポイントと、契約書作成で気を付けるべきポイントをまとめとしてお話しします。
まず、取引で気を付けるべきポイントとしては、以下の点が重要です。
- 対象となる取引先の洗い出し
◦ 従業員数基準が加わったことで、これまで下請法の対象外だった取引先が新たに中小受託事業者となる可能性があります。
◦ また、特定運送委託の追加により、運送業者との取引も新たに法の対象となる可能性があるので、こちらも見直しが必要です。
- 支払手段の現状調査と改善
◦ 手形払いが原則禁止となるため手形を利用している場合は現金または振込での支払いに切り替える準備が急務です。
◦ 電子記録債権やファクタリングを使用する場合も、支払期日までに満額を現金化できるかを確認し、困難な場合は使用を停止する必要があります。
- 振込手数料負担の廃止
- 価格協議の社内フロー整備と記録管理
◦ 価格協議が義務化されたため、中小受託事業者からの価格改定の求めに対し、適切に協議に応じ、必要な説明・情報を提供できる社内フローを整備する必要があります。
- 社内規定・マニュアルの作成と周知
◦ 改正法に対応した社内マニュアルを作成し、新たな義務、禁止行為、罰則、リスクについて全従業員に周知徹底する必要があります。研修や定期的なフォローアップを通じて、社員の理解を深めることが推奨されます。
- 支払サイト変更に伴う資金調達の検討
◦ 手形支払いから現金払いに切り替える企業は、急な資金繰りに支障をきたす可能性があります。また、60日の支払期限厳守が求められるため、運転資金が圧迫されることも考えられます。
次に、契約書作成で気を付けるべきポイントです。
- 用語のアップデート
◦ 契約書、見積書、発注書などの書面において、「下請法」「親事業者」「下請事業者」「下請代金」といった旧用語を、改正後の「中小受託取引適正化法」「委託事業者」「中小受託事業者」「製造委託等代金」に変更する必要 があります。
- 必要的記載事項の確認と書面交付義務の対応
◦ 改正法第4条(旧第3条)に基づく書面交付義務や、第7条(旧第5条)に基づく書類作成・保存義務に対応できるよう、既存の契約書類の記載内容が十分か精査が必要です。
◦ 中小受託事業者の承諾がなくても電磁的方法による書面提供が可能となったため、その運用準備も検討できます。
- 支払条件の見直し
◦ 契約書において、支払期日を給付の受領日から60日以内と明確に定め、手形払いを禁止する旨を記載する必要があります。現金化が困難な電子記録債権やファクタリングも使用できない点を反映させましょう。
- 価格協議に関する条項の追加
◦ 価格協議の義務化に伴い、契約書に中小受託事業者の費用変動等に応じた価格協議の求めに応じる旨や、協議のプロセスに関する条項を設けることを検討するべきです。
- 遅延利息の適用範囲の確認
◦ 減額された代金についても遅延利息の対象となる点が追加されたため、契約書における遅延利息に関する規定も、この改正に沿って適用されることを認識しておく必要があります。
福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。