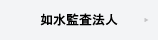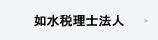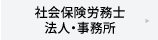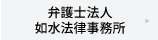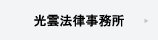成果物に関する権利の帰属
⑴ 成果物に関する権利の帰属
委託業務の遂行過程で知的財産権が生じうる場合、何も定めがなければ権利の帰属をめぐって争いが生じるリスクがあります。そのため、権利の帰属先を明確に定める必要があります。
特許法や著作権法では、特許権や著作権などの知的財産権は、原則として発明者や著作物を創作した者に帰属します(特許法29条1項、著作権法17条、2条1項2号)。そのため、委託業務の遂行過程で知的財産権が生じた場合、特に定めがなければ、これらは業務を遂行した受託者に帰属することとなります。
委託者に有利にする場合には、委託した業務の遂行過程で生じた権利を自由に行使できるよう、「本委託業務の遂行過程で生じる知的財産権は、全て委託者に帰属する」と定めるとよいでしょう。
一方、受託者としては自らが遂行した業務の過程で生じた知的財産権を自由に行使できるよう、「本委託業務の遂行過程で生じる知的財産権は、全て受託者に帰属する」と定めるとよいでしょう。この場合、委託者には業務委託の目的の範囲内で使用権を許諾するという条項を入れること委託者の権利を確保します。
著作権法上、注意しないといけないこととして、翻案権(著作権法27条)と二次的著作物の利用に関する権利(同法28条)については、「権利を移転することを示さなければ、譲渡した者に留まると推定する」とされている点があげられます(同法61条2項)。
そのため、権利の帰属先を定める際に、「著作権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む)」と明記する必要があることに注意してください。
⑵ 第三者の知的財産権の侵害について
委託者としては、成果物が、他人の知的財産権などの権利を侵害している場合、権利者からクレームや侵害訴訟等を提起されるリスクがあります。これを防ぐため、「成果物が他人の権利を侵害しないこと」を受託者が保証することを定めるとよいでしょう。これにより、万一、成果物が第三者の権利を侵害するものであったときは、受託者に契約違反を理由に、損害賠償や解除を求めることができます。
また、委託者が権利者から訴訟を提起された場合は、訴訟に応じなければならないなど、不利益を被るおそれがあります。
そのため、委託者としては、「第三者の権利に関する紛争が生じたときは、受託者がその責任と費用負担において当該紛争を処理し」、「委託者が紛争の当事者となった場合には、受託者は、委託者に対し、委託者が被った一切の損害を賠償しなければならない」と定めるとよいでしょう。
一方、受託者としては、成果物に、他人の知的財産権が含まれているかどうかを確認することができないなど、第三者の知的財産権を侵害する可能性を排除することが難しい場合は、「成果物が、第三者の権利を侵害しない」という条項を削除する必要があります。その上で更に、「成果物が、第三者の権利を侵害しないことを保証しない」と定めるとよいでしょう。ただし、これも経験上、相手方から「保証する」と修正を要望されやすい条項です。
業務遂行状況の報告義務
(1)民法の原則
民法では、準委任契約型の業務委託契約の場合、受託者は、委託者の請求に応じて、業務の遂行状況を報告しなければなりません(民法645条)。
一方で、請負契約型の場合は成果物を完成させるための手段は受託者に委ねられているため、受託者はこのような報告義務を負いません。
(2)報告義務に関する条項例
委託者としては、いずれの場合にせよ、委託した業務がどのような状況にあるのか、必要に応じて把握できるように、「受託者は、委託者の求めに応じて、本委託業務の遂行状況を委託者に報告しなければならない」と定めると有利です。
他方で、受託者としては、報告に応じることが難しい場合もあるため、このような報告義務を負わない旨を定めるか、そのような修正が難しい場合は、「必要な範囲で報告しなければならない」と定めるなど、報告する範囲を限定すると有利です。
また、委託者としては、期限までに業務を行ってもらう必要がある場合には、受託者が予定通りに業務を遂行することができないときは、早い段階で何らかの対応策を講じなければなりません。
そこで、「受託者は、本契約期間中に本委託業務を遂行することができないことが判明した場合、直ちに委託者に報告し、委託者の指示を受けなければならない」と定めるとよいでしょう。
(3)立ち入り検査に関する条項例
さらに、委託者として、受託者の業務の遂行状況をより適切に把握するため、「委託者は、本委託業務の遂行状況について監査をすることができ、必要に応じて、受託者の事業所において、立入検査をすることができる」と定めることもあります。
他方で、受託者としては委託者に監査権や立入検査を許容すると、営業秘密や顧客情報などが流出するリスクがあるため、このような定めは削除するか、削除が難しい場合には、「受託者の同意」や「受託者の事業に支障を与えないこと」を条件とするのが望ましいです。
再委託
(1)民法の原則
準委任契約においては、民法では、受託者は、「委託者の承諾」又は「やむを得ない事由」があるときでなければ、再委託することはできません(民法656条、644条の2 第1項)。一方で、請負契約においては、民法上、特に再委託は禁止されていません。
(2)再委託の承諾に関する条項例
いずれの場合にせよ、委託者としては、自らの知らないところで、受託者以外の他人に業務を遂行されたくない場合には、「受託者は、委託者の事前の承諾なく、再委託してはならない」と定める必要があります。このとき、同意の有無をめぐる争いを防ぐため、委託者の同意方式を「書面」とする旨を確認的に定めるとよいでしょう。
他方で、受託者としては、必要に応じて自由に再委託できるように、「受託者は、本委託業務の遂行に必要な範囲で、再委託できる」と定めると有利です。
(3)再委託先の責任に関する条項例
委託者としては、再委託を許容した場合には、再委託先が契約の定めに違反し、不利益をうける恐れがあります。これを防ぐために、「受託者は、再委託先に対して本契約上の受託者の義務と同等の義務を負わせる」と定めると有利です。
また、再委託先によって損害を被った場合に、受託者に民法上の債務不履行がなければ、損害賠償を請求できないおそれがあります。そこで、「再委託先によって委託者に損害が生じたときは、受託者も責任を負う」と定めることが望ましいです。
福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。
今回はNDA(秘密保持契約書)に続いて、2回目の契約書の読み方に関する説明のその1です。
今回取り上げる業務委託契約書も、契約書チェックをする際によく見る契約です。
業務委託契約の法的性質
まず、法的な位置づけとして、業務委託契約は、準委任又は請負もしくはその中間的な契約として位置づけられています。
民法では、準委任契約では、委託者が「事務を処理すること」を受託者に委託し、受託者がこれを承諾することによって効力が生じます(民法643条、656条)。
一方、請負契約では、受託者が「成果物を完成させること」を約し、委託者がその結果に対して報酬を支払うことを約することによって効力が生じます(民法632条)。
事務処理というプロセスに重点を置くか、成果物の完成という結果に重点を置くかによって準委任に近い契約なのか、請負に近い契約なのかという点が変わってきます。
まず、いずれの場合でもどのような業務を委託するのかを定めておく必要があります。
特に、業務内容をめぐる当事者間の認識の相違によってトラブルが生じることを防ぐため、どういった業務を委託するのか、具体的に定める必要があります。
このとき、委託者としては、依頼した業務を遂行するために必要となる雑多な仕事に関しても受託者に対処してもらえるよう、「その他委託業務に附帯関連する一切の業務」も業務内容として確認的に定めておくといいでしょう。
成果物の完成義務
上で説明したとおり、プロセスと結果のどちらに重点を置くかによって準委任に近いか、請負に近いかが変わってきます。
そして、結果に重点を置く場合には、委託者としては、成果物が契約の内容に適合しなかった場合に受託者に対して責任を追及できるよう、「受託者は成果物を完成させる義務を負う」と定めるとよいでしょう。
一方、受託者としては、成果物を完成させることができるかどうかが分からない場合は、「受託者は、成果物の完成義務を負わない」と定めるとよいですが、このような条項があると完成義務を負う内容への修正の要望が生じることも多いです。
法令等の遵守義務
また、委託者としては、委託者が遵守すべき法定等の規則を受託者にも遵守させた上で業務を遂行させることができるよう、「受託者は、本委託業務の遂行に関して委託者に適用される法令等の規則を遵守しなければならない。」と定めることがあります。
一方、受託者としても、法令遵守はある意味当然の義務とはいえますが、業務を遂行するにあたって、どのような規則を守る必要があるのかを明確にするために、
「委託者は、本委託業務の遂行に関して委託者に適用される法令等の規則の内容を通知しなければならない」と定めることもあります。
⑴ 民法の原則
委託料をめぐってトラブルにならないように、金額を明確に定める必要があります。
また、契約が途中で終了したときのトラブルを防ぐため、「委託料が履行割合に応じて発生するのかどうか」を定めておくとよいでしょう。
民法では、準委任契約でも請負契約でも、委託者の責任によらずに、契約が途中で終了したときは、委託者は履行割合、もしくは仕事の結果のうち可分な部分の給付によって受けた利益の割合に応じて、報酬を支払わなければなりません(民法656条、648条3項、648条の2第2項、634条)。
なお、これは、受託者の責任で契約が途中で終了したときも同様です。
一方、委託者の責任で契約が途中で終了したときは、委託者は報酬の全額を支払わなければなりません(同法536条2項)。
⑵ 委託者の帰責性によって契約が途中で終了したときの修正
上で述べたように、民法では、委託者の帰責性によって、契約が途中で終了したときは、委託者は報酬の全額を支払わなければなりません。
そのため、委託者に有利にする場合には、委託者の責任で契約が終了した場合でも、履行割合に応じて報酬を支払えば済むように、「委託者の帰責事由によって本契約が終了した場合、委託者は、履行割合を乗じた金額を受託者に支払う」と定めるとよいでしょう。
一方、受託者に有利にする場合には、自らに責任がない限りは報酬の全額を請求できるように、「受託者の帰責性によらずに契約が途中で終了したときは、委託料の全額を請求できる」と定めるとよいでしょう。
民法の規定通りとする場合は、「委託者の帰責事由によって、本契約が終了した場合、委託者は委託料の全額を支払う」と定めておきます。
⑶ 受託者の帰責性によって契約が途中で終了したときの修正
民法では、受託者の責任によって、契約が途中で終了したときであっても、委託者は履行割合、もしくは仕事の結果のうち可分な部分の給付によって受けた利益の割合に応じて、報酬を支払わなければなりません。
委託者としては、受託者の帰責性によって契約が途中で終了した時は、報酬を支払わなくても良いように、「受託者の帰責性によって契約が途中で終了したときは、委託料は発生しない」と定めるとよいでしょう。
福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。